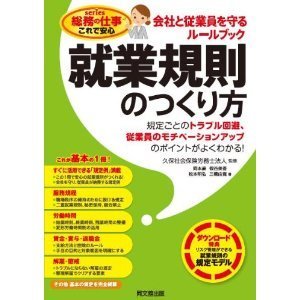〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘4-56-3
営業時間:平日 9:00~18:00
【就業規則における「パートタイマー」】
「パートタイマー」という言葉、就業規則を拝見させていただくと、
会社によってその名称や定義(適用範囲)が異なります。
名称でいえば
「パートタイマー」「パートタイム従業員」「パート社員」にはじまり、
「契約社員」「準社員」「臨時社員」などなど・・・
定義内容(文言)も少しずつ違いますね。
これはこれで全く構いません。
【法律における「パートタイマー」】
実は、「パートタイマー」とはこういう人達です!という定義が
“法律”でもされています。
「パートタイム労働法」という法律をご存知でしょうか。
正式には
「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」
と言います。
・・・長いので、
一般的に「パート労働法」「パートタイム労働法」などと呼ばれています。
この法律において、次のように定義されています。
「パートタイム労働者とは、
1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される
通常の労働者の1週間の所定労働時間と比べて短い労働者」
つまり、
①通常の労働者(つまり正社員)ではない人
=期間雇用労働者
②週の所定労働時間が短い人
=短時間労働者
をまとめて「パートタイム労働者」とし定義しているんですね。
「あれ、そういう法律上の定義があるなら、
就業規則の中の“パートタイマー”の定義も
これ合わせなければいけないのかな?」
という疑問が出るかもしれませんが、そんなことはありません。
就業規則におけるパートタイマーの範囲を
パートタイム労働法の“パートタイマー”の定義に
あわせる義務はありません。
この法律は名称からもイメージできるように、
非正規雇用者、短時間労働者の雇用環境を整備することを目的としています。
「対象範囲広く、名称にかかわらず、こうした人達はこの法律で守りますよ〜」
というイメージです。
一方の就業規則ではその名称ごとに社内における違いがある
(だからこそ区分しているんですよね!)わけですから、
その区分をむしろ明確にしておかなくてはなりません。
逆にいうと、
就業規則で“アルバイト”と定義されている従業員であっても、
上記①または②の要件を満たしていれば、
当然「パートタイム労働法」の対象者になります
ので要注意!
ここは勘違いされていることがあるので、
是非おさえておいていただきたい所ですね。
お問合せ・ご相談はこちら
受付時間:平日 9:00~18:00
経営者・人事労務担当者のみなさまへ
神奈川県座間市の社会保険労務士岡本事務所です。
就業規則は労使トラブルを回避し、社員との信頼関係を築く重要アイテムです!
このサイトでは「就業規則ってどんなものか知りたい!」
というあなたのために、よく見かける“就業規則サンプル”を題材に就業規則作成(変更)のポイントをわかりやすくお伝えいたします。
Twitter(ツイッター)@take_okamoto
| 対応エリア | 神奈川県横浜市、川崎市、相模原市、座間市、厚木市、海老名市、大和市、綾瀬市、その他神奈川全域、東京都内など |
|---|
変更入門
作成入門
サンプル規程チェック
自分だけで就業規則を作るのは不安なあなたへ
事務所紹介
プロフィール
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
「元気な会社作り」のお手伝いをしています。
ポイントは【攻めと守りを意識したルール作り】!